第10回博士後期課程学生交流会が令和5年2月16日(木)18時00分よりオンライン会議システム(Zoomミーティング)を用いて開催されました。本交流会は、同期といえる近い世代が研究室や専攻内に少ない博士後期課程の学生に、専門分野を超えて学生間で世間話のできる関係を築き、教員との対話の中から自身の研究に活かせるヒントを発見して欲しいとの思いから企画されているものです。
本年度は、コロナ禍による2年間の中断を経て、3年ぶりの開催となりましたが、駿博会会長の理工学部長はじめ、駿博会理事の大学院担当にご参加いただきました。博士後期課程の在籍学生には直接電子メールで参加を呼びかけ、6専攻10名の学生の参加がありました(在籍学生は39名)。さらに、駿博会総務委員の教員を含めた22名の参加者となりました。
交流会は宇於﨑勝也総務委員の司会で開始となり、駿博会会長の青木義男理工学部長から、コロナ禍で研究活動に困難をきたしたことは十分に承知しているとの慰労の言葉と、酒井健夫学長が掲げる「日本大学ルネサンス計画」において『総合知』が掲げられ、総合大学だからこそできるジャンルを広げた研究、学部連携の取り組みが社会から注目され始めているという現状の紹介がありました。続けて駿博会の吉川浩総務委員長による主旨説明があり、中川活二大学院担当からは孤立しがちな博士後期課程学生の重要な交流会になるとのお話をいただきました。
司会より、まず各自数分で自分の研究テーマと自己紹介を分かりやすくしてくださいとの依頼があり、各自がそれぞれの言葉で表現しました。
<<以降の懇談内容に関しては、会員ページで掲載しています>>

交流会は話が尽きませんでしたが、記念撮影をして1時間30分で終了となりました。
オンライン開催は初めての試みでしたが、プレゼンテーションツールを用いたり、実際に研究や実験を行っている場からつないだことで、具体的に制作した作品や試料、実験室の様子などのリアルを見ることができて、よい点も多くありました。次年度はぜひ対面の懇親・交流会を開催したいと思います。
本交流会をきっかけに参加者同士の交流がいずれ理工学部の発展に寄与するよう期待されてやみません。
第9回博士後期課程学生交流会が令和2年2月20日17時30分より駿河台校舎1号館2階カフェテリアで開催されました。本交流会は、同期といえる近い世代が研究室や専攻内に少ない博士後期課程の学生に、専門分野を超えて学生間で世間話のできる関係を築き、教員との対話の中から自身の研究に活かせるヒントを発見して欲しいとの思いから企画されているものです。
本年度も駿博会会長の理工学部長はじめ、駿博会理事の理工学研究所長、大学院担当にご出席をいただき、各専攻の主任にも参加を呼びかけました。さらに、博士後期課程の在籍学生には参加を呼びかける案内を直接送付し、9専攻13名の学生の参加がありました。さらに、教員や駿博会総務委員、交流会OBなどの教員と理工学部校友会長を含めた49名の出席者となりました。
交流会は伴周一総務委員の司会で約10分遅れて開始となり、駿博会会長の岡田 章理工学部長から、本交流会の参加者が新任教員となって活躍しているので、諸君たちにも後に続いてもらいたいという励ましのご挨拶をいただきました。続けて駿博会の三浦光総務委員長による主旨説明に続き、木田哲量理工学部校友会長からは学位取得者へのお祝いとともにご祝辞をいただき、あわせて乾杯のご発声をいただきました。
交流会の中では学生による専門用語から平易な語り口調までさまざまな特徴のある研究紹介があり、歓談中には会場の随所で教員・学生間の懇親・交流が見られました。
また、中田善久大学院担当から博士後期課程学生に向けてメッセージがあり、学生数が少ない中でもよい研究が行われているという評価をいただきました。
交流会は盛会のうちに1時間40分で中締めとなり、青木義男船橋校舎次長から学生に対する期待が述べられ、1本締めでお開きとなりました。その後も会場で歓談が続けられ、2時間を経過した本締めでは高野良紀駿河台校舎次長から閉会のご挨拶があり、解散となりました。
例年よりも博士後期課程学生の参加者は多かったものの、教員の参加者数のほうが多い状況は例年のことですが、分野を超えて他専攻の教員からも意見をいただける場でもあり、博士後期課程の学生数がもっと増えることが望まれます。
本交流会をきっかけに参加者同士の交流がいずれ理工学部の発展に寄与するよう期待されてやみません。






第8回博士後期課程学生交流会が平成31年2月21日17時より駿河台校舎1号館2階カフェテリアで開催されました。本交流会は、同級生といえるような近い世代が研究室や専攻内に少ない博士後期課程の学生に、専門分野を超えて学生間で世間話のできる関係を築き、教員との対話の中から自身の研究に活かせるヒントを発見して欲しいとの思いから企画されているものです。
本年度も駿博会会長の学部長、駿博会理事の理工学研究所長、大学院担当にご出席をいただき、各専攻の主任にも参加を呼びかけました。さらに、博士後期課程の在籍学生には参加を呼びかける案内を直接送付し、7専攻10名の学生の参加がありました。さらに、教員や駿博会総務委員、交流会OBなどの教員と理工学部校友会長を含めた36名の出席者となりました。
交流会は伴周一総務委員の司会で約10分遅れで開始となり、駿博会の三浦光総務委員長による主旨説明に続き、駿博会会長の岡田 章理工学部長から、昨年度の参加学生が4月から新任教員となって、辞令を渡す際の喜びを含め、後輩たちにも後に続いてもらいたいという励ましのご挨拶をいただきました。木田哲量理工学部校友会長からは学位取得者へのお祝いとともにご祝辞をいただき、あわせて乾杯のご発声をいただきました。
交流会の中では学生の研究紹介を交えた自己紹介やハマっていることが語られ、歓談中には会場の随所で教員・学生間の懇親・交流が見られました。
また、内木場文男理工学研究所長や中田善久大学院担当から博士後期課程学生とその指導をする教員に向けてメッセージがあり、よい学生をたくさん育てたいという抱負とも受け取れました。
交流会は盛会のうちに1時間40分で中締めとなり、高野良紀駿河台校舎次長から学生に対する期待が述べられ、3本締めでお開きとなりました。その後も会場で歓談が続けられ、2時間を経過した本締めでは青木義男船橋校舎次長の「蛍の光」斉唱とともに閉会のご挨拶があり、解散となりました。博士後期課程学生よりも教員の参加者が多い状況は例年のことですが、分野を超えて他専攻の教員からも意見をいただける場でもあり、博士後期課程の学生数がもっと増えることが望まれます。
本交流会をきっかけに参加者同士の交流がいずれ理工学部の発展に寄与するよう期待されてやみません。



第7回博士後期課程学生交流会が平成30年2月23日17時より駿河台校舎1号館2階カフェテリアで開催されました。本交流会は、同級生といえるような近い世代が研究室や専攻内に少ない博士後期課程の学生に、専門分野を超えて情報交換や世間話のできる機会を持ってもらい、情報交換の中から自身の研究に活かせるヒントを発見して欲しいとの思いから企画されているものです。
本年度も駿博会会長の学部長、駿博会理事の理工学研究所長、大学院担当にご出席をいただき、各専攻の主任にも参加を呼びかけました。さらに、博士後期課程の在籍学生には参加を呼びかける案内を直接送付し、7専攻11名の学生の参加がありました。さらに、教員や駿博会総務委員、交流会OBなどの教員27名と理工学部校友会長を含めた39名の出席者となりました。
交流会は伴周一総務委員の司会でほぼ定刻に開始となり、駿博会の堀内伸一郎総務委員長による主旨説明に続き、駿博会会長の岡田 章理工学部長から、自身の博士後期課程での経験にもとづく励ましのご挨拶をいただきました。木田哲量理工学部校友会長からは学位取得者への期待とともにご祝辞をいただき、あわせて乾杯のご発声をいただきました。
交流会の中では学生の研究紹介を交えた自己紹介が行われ、歓談中には会場の随所で教員・学生間の懇親・交流が見られました。
交流会は盛会のうちに1時間30分で中締めとなり、青木義男船橋校舎次長から学生に対する期待が述べられ、ニホン締めでお開きとなりました。その後も会場で歓談が続けられ、2時間を経過した本締めでは内木場文男研究所長から閉会のご挨拶があり、解散となりました。博士後期課程学生よりも教員の参加者が多い状況は例年のことですが、他専攻の教員と意見交換できる意義のある場でもあり、博士後期課程の学生数がもっと増えることが望まれます。
本交流会をきっかけに参加者同士の交流がいずれ理工学部の発展に寄与するよう期待されてやみません。



第6回目となる博士後期課程学生交流会が平成29年2月16日18時より駿河台校舎1号館2階カフェテリアで開催されました。今回は例年の12月から2月へと開催日を移動しての開催です。これは学位申請論文の審査が終わって学生も教員もホッとした時期のほうが参加しやすいと考えたからです。本交流会は、入学者数が減少し、同級生といえるような近い世代のいない博士後期課程の学生に、専門分野を超えて情報交換を行って欲しい、情報交換の中から自身の研究のヒントとなるような新たな発見をして欲しいとの思いから企画されたものです。
本年度も学部長、駿博会理事でもある理工学研究所長、並びに大学院担当に出席をたまわり、理工学研究科の大学院委員会委員にも参加を呼びかけました。さらに、博士後期課程在籍学生には直接参加を呼びかける案内を差し上げて8専攻13名の学生の参加がありました。両校舎次長、専攻主任、大学院委員会委員、駿博会総務委員、交流会OBなどの教員ほか35名と理工学部校友会長を含めた49名の出席者となりました。
交流会は伴周一総務委員の司会で定刻に開始となり、駿博会の堀内伸一郎総務委員長による丁寧な主旨説明に続き、駿博会会長である山本 寛理工学部長から、博士後期課程への進学学生数の減少の危機感とともに、論文審査を終えて修了見込みとなった学生への期待と、在学生に対する励ましのご挨拶をいただき、深澤豊史理工学部校友会会長による、自身も駿博会設立時の最初の会員であるというエピソードとともにご祝辞をいただき、あわせて乾杯のご発声をいただきました。
交流会の中では学生からの研究紹介を交えた自己紹介が行われ、歓談中には会場の随所で教員・学生間の懇親・交流が見られました。
交流会は盛会のうちに1時間30分で中締めとなり、原田 宏駿博会理事から理工学部や学生に対する期待が述べられ、三本締めでお開きとなりました。その後も会場で歓談が続けられ、2時間の本締めでは司会から解散を促されました。本年度は開催時期を変更したこともあり、参加者数も増えて交流会の目的を達したのではないかと思われます。本交流会をきっかけとする参加者同士の交流がいずれ理工学部の発展に寄与するよう期待してやみません。
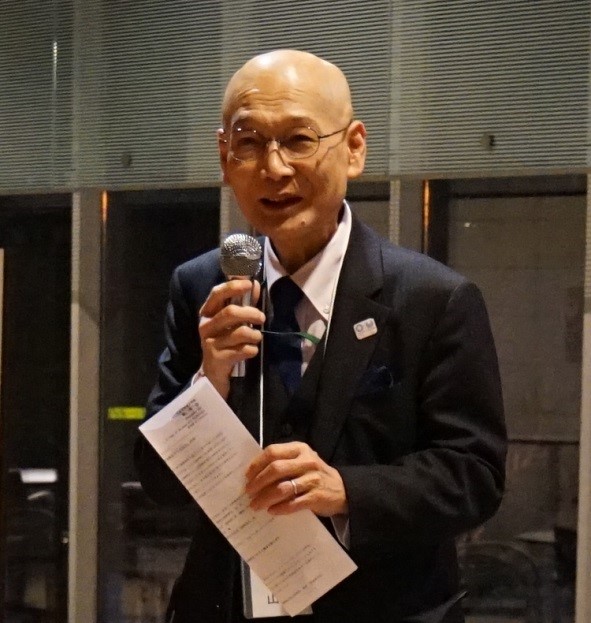
山本 駿博会会長からのご挨拶

深澤 理工学部校友会長からのご挨拶

原田 駿博会理事の中締め
博士後期課程学生交流会が平成27年12月5日、理工学部学術講演会終了後の18時より駿河台校舎1号館2階カフェテリアで開催されました。本交流会は、年度によっては専攻に1~2名の在籍学生となり、交流を持ちにくい専門分野の異なる博士後期課程の在籍学生が互いに知り合い、専門を越えての情報交換を行って欲しいとの思いから企画されたものです。
本年度は駿博会理事の学部長、大学院担当、理工学研究所長に出席をたまわるとともに、理工学部の大学院委員会委員にもお声がけをして、一部の先生にはご出席いただきました。また、博士後期課程在籍学生には直接参加を呼びかける案内を差し上げ、その結果、7専攻10名の学生と、専攻主任、大学院委員会委員、駿博会総務委員などの教員25名と理工学部校友会長を含めた36名の出席者となりました。
本年度の交流会は、駿博会総務委員長の堀内伸一郎教授による主旨説明に続き、駿博会会長・理工学部長の山本 寛教授から、博士後期課程学生数の減少の危惧と、指導教授のみならず専攻を越えて教員の指導を積極的に受けるようにとの学生への鼓舞を含めたご挨拶をいただき、例年ご出席いただいている深澤豊史理工学部校友会長による、専攻を越えての交流の意義に関するご祝辞にあわせて乾杯のご発声をいただきました。
交流会の中では学生からの研究紹介を交えた自己紹介が行われ、歓談中には会場の随所で懇親・交流が見られました。ご出席いただいた理事の原田 宏先生には学生への質問を兼ねたご挨拶をいただきました。さらに、専攻内説明会を間近かに控えた3年生の学生も参加しており、公聴会に向けての決意も語られました。
交流会は盛会のうちに1時間30分で中締めとして岡田 章次長のお言葉、2時間で締めとして青木義男次長のお言葉をいただきましたが、それぞれご自身が学位取得をされたころの体験をもとに参加学生へのエールを送るものとなりました。本年で5回目となる交流会ですが、その目的を達したのではないかと思われます。本交流会をきっかけとする参加者同士の交流が、いずれ理工学部の発展に寄与するよう期待してやみません。
 |
 |
| 山本 駿博会会長からのご挨拶 | 深澤 理工学部校友会長からのご挨拶 |
博士後期課程学生交流会が平成26年12月6日、理工学部学術講演会終了後の18時より駿河台校舎5号館1階学生食堂で開催されました。本交流会は、日ごろその専門性のゆえに、あまり交流を持つことのない異なる専門分野の博士後期課程の在籍学生同士が知り合い、専門を超えての情報交換を行って欲しいとの思いから企画されたものです。
本 年度は駿博会理事の学部長、大学院担当、理工学研究所長、事務局長に出席の要請を行うとともに、理工学部の大学院委員会委員にもお声がけをし、理工学部の 学生への教育・研究に対する支援とも協力関係にあることを知っていただくように努めました。また、博士後期課程在籍学生には直接参加を呼びかける案内を差 し上げました。その結果、10専攻15名の学生と4名の教員、駿博会総務委員9名を含む理事11名、また例年ご出席を賜る理工学部校友会長を含めた、31名の出席者となりました。
本 年度の交流会は、駿博会総務委員長の堀内伸一郎教授による主旨説明に続き、駿博会会長・理工学部長の山本 寛教授から、学生に向けて大いに期待している旨 のご挨拶をいただき、ご自身も駿博会会員である深澤豊史理工学部校友会長による、学位取得の苦しみと楽しさの経験についてのご祝辞をいただき、続けて乾杯 のご発声をいただきました。
交 流会の中では学生からの研究紹介を交えた自己紹介が行われ、歓談中には会場の随所で懇親・交流が見られました。ご出席いただいた教員の皆様には一言ずつご 挨拶をいただきましが、博奨励賞受賞者で、本年度から一般教育の助手になられた梅津光一郎先生や、交流会OBで電気工学科助手の淺見拓哉先生は学生たちと 年齢が近いこともあり、学位取得までの苦労やその後の経験などが語られました。専攻内説明会を間近に控えた3年の学生も参加しており、エールの交換なども ありました。
交流会は盛会のうちに2時間で中締めとなり、4回目となる本年度も目的を達したのではないかと思われます。本交流会をきっかけとする参加者同士の交流が、いずれ理工学部の発展に寄与するようなプロジェクトに育つよう期待してやみません。

山本 駿博会会長からのご挨拶

深澤 理工学部校友会長からのご挨拶